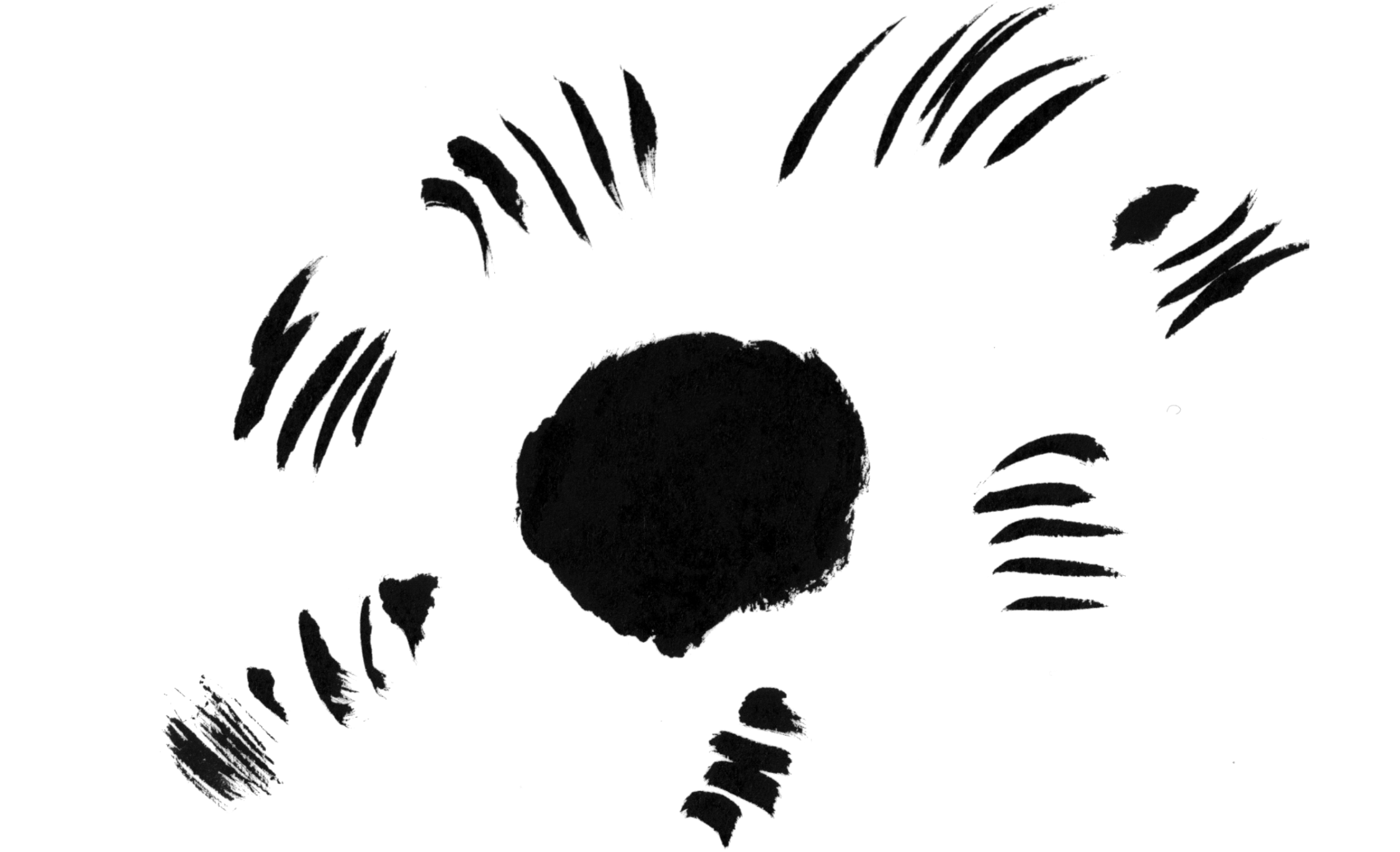
髪を切るということ 10
アトリエにて
石田 千 / 作家
ながいながい巣ごもりだった。地下鉄に乗った。髪を切りにいく。
鎖骨がかくれると、鏡を見ながら切っていた。ふたつにわけて、ゴムで束ねて、ばっさり。そういうふうに、三年くらいしのいでいた。
ごぶさたしていました。
首にタオルを巻いて、ケープにくるまる。
……前髪、なくなっていますね。
まえは、ぱっつん切っていただいた。巣ごもりのあいだは、ひっつめているほうが、清潔でいられると思って、そのまま伸ばした。
おそるおそる世のなかにもどるにあたり、可能なかぎり、みじかくしていただきたい。そう決めてきた。こまったときは、すぐかわくから、石けんで洗えばいい。ひといちばい怖がりで、いまも部屋を出るときは、勇気をお与えください。父の写真に手をあわせる。
ざんばら髪に、ていねいに、櫛が通る。
シャンプーのときは、とても怖かった。お医者さんのほか、ずっと、だれも触らなかったから。それでも、あたたかな湯がながれて、泡がたち、よい香りにつつまれたら、よろこびが怖いをつつんで、流してくれた。
鏡のまえにすわって、決めてきたことをお伝えした。
まず、肩まで。それだって、ずいぶん、ばっさりの感じだった。それから、耳のしたで、そろえて、おかっぱ。いつかまた、このくらいまで、伸ばせるといいなあ。
そこから、さらに耳があらわれ、前髪も、どこもかしこも、首をふってもなびかない。もう切るところはないくらいになって、安心した。
三十代いらいの、短髪。思ったより、しろくないな。ずっと染めてもらっていたし、束ねていたから、わからなかった。やせっぽちになって、ひびだらけの手で、ようやく、いまを見つけた。

なにより、朝、手をあわせていた写真の父に、そっくりだった。お父さんの髪は、お山がふたつ、つらなっているようです。小学校の作文で書いた。七三の、その分けめも、おんなじだった。
五十五のころの父は、もっと元気で、毎日ビールもおさけも飲んでいた。これから、あんなふうに暮らせたらいいな。
ああ、これからは、だんだん、もっと、みんなに会えるようになる。きっと、よくなる。
いらい、できるだけ毎月、髪を切っていただく。毎月いかなくても支障はないほどみじかいけれど、泡にくるまれ、鋏で切り祓われ、身からはなれる。そのなにかの気配を、鏡ごしに見ている。
父は、毎週末、理髪店に通っていた。八十をすぎると、綿のように、まっしろでふっくらしていた。長生きできたら、そうなるかもしれない。
いまは、毎朝の寝ぐせがたのしい。
安藤忠雄さん、コボちゃん、きのうはインコだった。
毎朝、声をたてて笑う。
みじかくして、ほんとうによかった。

石田 千ISHIDA Sen
作家
1968年福島県生まれ、東京育ち。國學院大學文学部卒業後、嵐山光三郎事務所に勤務。2001年雑誌「彷書月刊」にて第1回古本小説大賞を受賞。いらい、執筆活動をつづけている。近著に、「窓辺のこと」「月金帳」(いずれも港の人)など。
